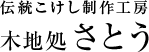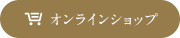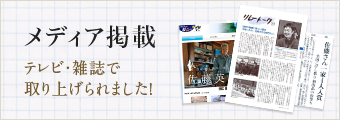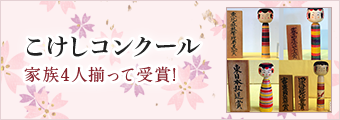7月1日は、私佐藤英之にとって特別な日でした。 ちょうど10年前の6月30日に、大阪で勤務していた会社を退職しました。 こけし家業を継ぐ決心で故郷福島へ旅立ったのが、10年前の7月1日だったんです。 あれから10年。いろ…
こけし修行記
平成24年のご挨拶を申し上げます
みなさま新しい年をいかがお迎えでしょうか? 昨年度は大変な震災を経験しましたが、多くのみなさまの支えのおかげで、木地処さとうは家族元気で新年を迎えることができました。 本日は、新しい年のご挨拶とともに、木地…
さくらんぼ
赤城山の山荘。庭の桜の木に、なんとさくらんぼが実った! まさかさくらんぼだったとは。小粒で少しすっぱいけど、とってもおいしい。 来れる方は食べに来てください(笑) いわきに、庭にさくらんぼの木があるという仲間がいた。 で…
津波に遭ったこけし
先日、いわきに一時帰宅したときに手に入ったこけし。 新舞子という海岸近くに位置する、新舞子ハイツ。 ここには長い間、うちのこけしが委託販売で、お土産に置かれていました。 浜辺から50メートルと離れていない新舞子ハイツには…
赤城山工房への地図
赤城山の工房へ、自動車でお出かけの方へ。 どうやら、自動車のナビゲーションではたどり着けないことが判明いたしましたΣ(゚ロ゚ノ)ノ 住所は以下の通りですが、できればこちらの地図を持っていらしてください。 〒3…
赤城山の工房ができてきた
壁のない、わが赤城山の工房をご紹介して1週間。 男手3つで作業を続け、ようやく形になってきたのでお見せします! ずいぶん変わったでしょ!?なんと部屋が二つになりました。 左側のロクロがある部屋には藤棚の形跡が見えます。 …
本式のロクロが動き出す
裏の物置を片付けて、こけしの工房に改造してから2週間。 やはり実演用の小さいロクロでは仕事が限られてしまうということで、本式のロクロを持ってこようと計画を練っていました。 本式のロクロは実演用とどう違うのか? まずやぐら…
赤城山こけし、販売始めました。
赤城山にある、創作こけしの工房、藤川工芸さんにご提供いただいて、群馬県産のミズキで今後こけしを製作することになりました(^ω^)ほんとありがたい。感謝です。 今まで使ってきた木材は、全て東北産のものだった。そ…
赤城山でのこけしができた!
昨日、4月4日。 震災から25日目にして、僕はやっとこけしを作り始めることができた。 ずいぶんやってないと、勘が鈍るもんです。どうもいつもどおりにはいきません。 でもともかく一つ、仕上げてみることが大事と肝に命じ、無心で…
ボランティアけん玉
赤城山に来てから今日で13日目。もうすっかり慣れてきて、少し余裕もできてきました。 昨日の日曜日は、近くにある避難所へ行ってボランティアでけん玉を披露・教室もやってきました! 僕達は恵まれている避難者だから、できることは…