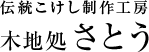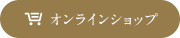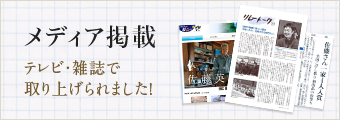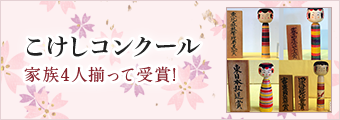小川の工房作りが本格的に始まった(・∀・) 最初に暑さ対策ということで、天井の裏側にグラスウールの断熱材を入れて、塗装した板を貼る作業。 ただでさえ暑いのに、ワタの…
こけしの郷便り
新工房計画のお知らせ
久々のこけしの郷便りとなりました。今日は新工房計画をお知らせしたいと思います! 木地処さとうの工房は、1982年に現在の福島県いわき市平塩(以下平工房とします)に二代目の誠孝さん一人で始まりました。その後2001年に三代…
こけし展 木の香銀座 のお知らせ
みなさまあけましておめでとうございます(^^) いつも木地処さとうのホームページをご覧くださりありがとうございます。 本年もどうぞよろしくお願いいたします。 今年最初のこけしの郷便りは、銀座でのこけし展のお知らせです。 …
お彼岸こけし
お久しぶりのこけしの郷便りとなりました。 暑い夏も終わり、気が付けばもうお彼岸ですね。暑さ寒さも彼岸までと言われますけど、東北にはその通り秋の気配を感じることができます。 今週は5日ほど嫁の里帰りに付き添うことになりまし…
特別注文品についてのお知らせ
今日はよくお問い合わせいただく内容の中で、ホームページでは紹介されていない作品のご注文についてお話しいたします。 ホームページで販売されている作品はごく一部で、ブログのみで紹介されているものやホームページ内に写真だけが…
伝統こけし 誠古型ロクロ
こんにちは!三代目英之です。 すっかり夏本番となりましたね~。 私事で恐縮ですが、8月2日に誕生日を迎えまして、37歳になりました。 毎年誕生日の思い出といえば、暑い!ということが最初に来ます。なんだかんだ言いながら夏が…
【こけしの郷便り】若手工人兄弟
こんにちは!三代目英之です。 今日は珍しく、兄弟で同じ部屋でこけしの描彩をしておりました。 伝統こけしは、すべての工程を一人で行うのが基本。それが工人と呼ばれる所以です。 ですから、こうやって同じ部屋でこけしを描いていて…
【こけしの郷便り】ねむりえじこ製作中
こんにちは!三代目英之です。 本日はねむりえじこを作っておりました。 ねむりえじこといえば、わが工房の中ではとても人気が高い作品なんです。 特に今年は日生協のカタログでもトップで紹介されたこともあって、今までにないくらい…
【こけしの郷便り】誠旧型直胴椿
こんにちは!三代目英之です。たまには工房のお話をしたいと思います(^-^)。 木地処さとうは、主に誠孝さん、英之、裕介さんの3工人が日々こけしを作っているので、毎日いろんなこけしが出来上がっています。 裕介さんは時々「一…
【重要】消費税についてお知らせ
いつも木地処さとうをご愛顧いただき誠にありがとうございます。 みなさんご存知の通り、本年4月1日から消費税が8%になりました。 木地処さとうでは世の中の様子を見て、必要な場合には消費税のご負担をお願いすることにしており…